『哀れなるものたち』 やってみてわかること、やらないでもいいこと
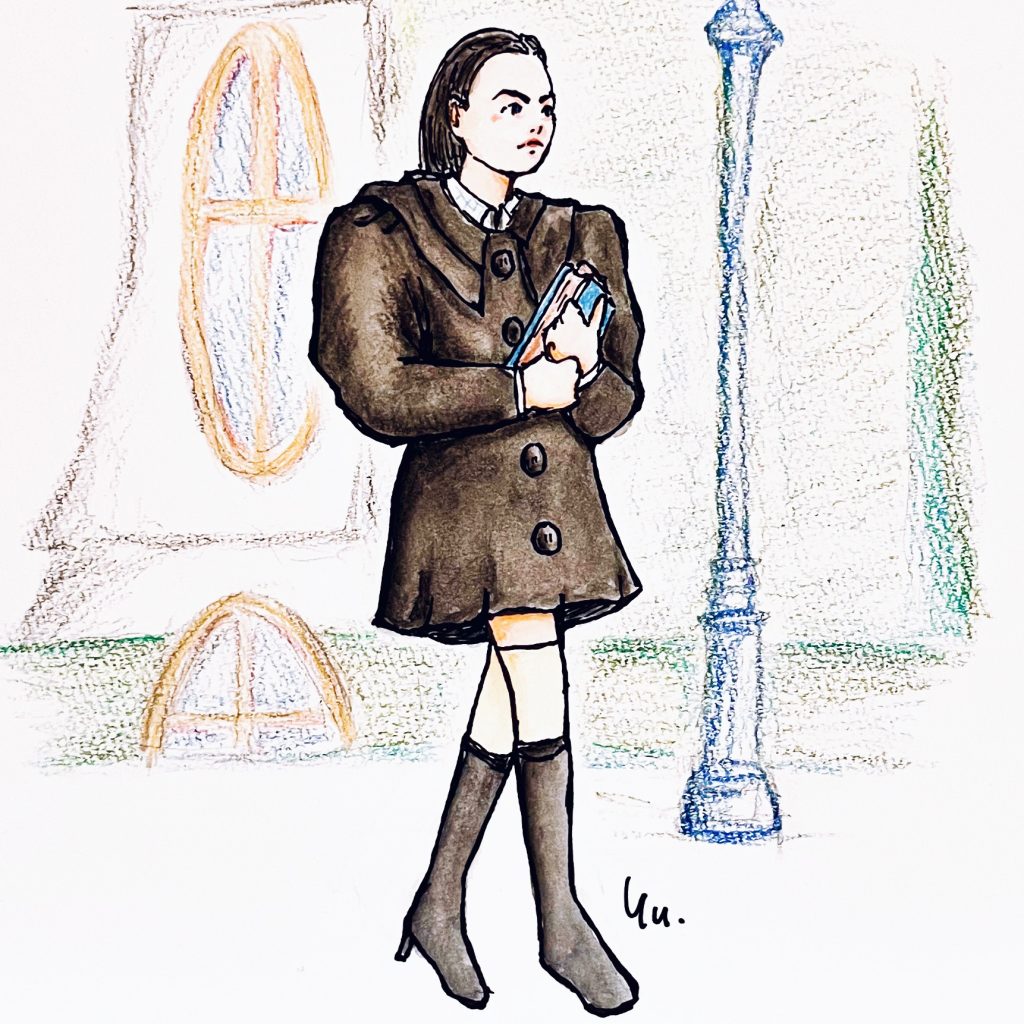
ヨルゴス・ランティモス監督の最新作『哀れなるものたち』が日本で劇場公開された2024年1月、SNSでは絶賛の声の嵐となった。なんだか小難しい考察が流れてくるので、すこし難解な作品なのかもしれない。フェミニズム映画と言われてしまうと、昨今の映画の流行りなので、どうしても構えてしまう。でも昨年末の海外から流れてくる、抽象画のようなポスタービジュアルや、美意識の高い絵づくりの予告編は、「この映画を観ない訳にはいかない!」と思わせるパワーがあった。
こんなつくりこまれた映画なら、ぜひ劇場で観てみたいと思った。自分はこの映画が日本で公開になってから興味を持ったので、映画館に向かおうと決めたのはすこし遅れをとってしまった。公開2週目には、すでにこの映画はどこのシネコンでも1日1回しか上映していない。しかも朝8時のモーニングショーや夜9時からのレイトショー、せいぜい夕方4時からの上映と、生活を考えるととても観づらい時間設定に追いやられている。もう映画館に来てくれるなと、無言の圧すら感じてしまう。
昨今、日本のシネコンはアニメしか上映していないというのが問題となっている。実際、映画館に足を運ぶ客層の多くは、アニメ作品や、大手広告代理店の元で大仰に宣伝されている国内作品がメインとなっている。観客にしてみれば、映画館に映画を観にいくというよりは、好きな作品のイベントに参加するという感覚に近いのかもしれない。
コロナ禍以降から配信サブスクが生活にすっかり溶け込んでしまった。家で映画を観るのも、TSUTAYAなどのレンタルショップからDVDを借りて観るスタイルから、サブスクで気が向いたときに観るスタイルにと、完全にシフトチェンジしてしまった。コロナ禍で映画館へ行くのもはばかれる時期を越えたせいか、劇場に足を運ぶ習慣が途絶え、劇場に行くこと自体が億劫になってきた。チケット代の高騰も足が遠のく原因として大きい。それに海外作品は、今では早ければ劇場公開から2ヶ月もすれば配信が始まってしまう。これでは映画館へは行かなくなる。洋画の不人気というよりは、映画館で映画を観る人が激減したと捉えた方がいい。
作品を配給する側も、劇場公開の重要性よりも、いち早くサブスクに載せることの方が優先されているようにも感じる。作品によっては、日本劇場公開さえされずに配信スルーされるものもある。今までも、日本での海外作品の公開は、世界で一番最後の方だったりする。肩書きや周りの目を気にする日本人。何かの賞を獲ったり、どこかの国でメガヒットを出した経歴がないと、なかなか作品自体に興味を示さない。同調圧力の習性。そんなこんなで待っているうちに、海外公開から一年後の忘れた頃に日本公開されることとなる。そうなるくらいなら、早々に配信スルーで観れてしまった方がいい。もう映画を映画館で観る時代が終わったのかもしれない。実際この『哀れなるものたち』も、劇場公開3ヶ月後の4月には配信が始まった。このスケジューリングが、映画配給の今どきのビジネススタイルとして、すでに確立されているのだろう。
『哀れなるものたち』の劇場での鑑賞を早々に諦めた自分は、ヨルゴス・ランティモス監督の過去作品を観てみることにした。彼の作品はよく話題にされていて、タイトルだけなら、どれも聞いたことがある。中でも『ロブスター』はヨルゴス・ランティモスの名前を知る前から、興味を持っていた。
『ロブスター』は、コリン・ファレル主演のラブコメとのこと。パートナーがいないことを咎められる社会が舞台の物語。単身者が限られた日数で相手を見つけられなければ、動物にされてしまうという。コリン・ファレル演じる主人公は、動物になるならせめてロブスターになりたいと言う。プレイボーイで浮き名を流すことの多いコリン・ファレルが、相手がいなくて困るなんてあり得そうもない。なんたる皮肉と、ゲラゲラ笑うつもりでこの映画を観た。観てみると、思っていたのとぜんぜん違う。作中の世界があまりにディストピア過ぎて、どーんと落ち込んでしまった。社会風刺は好きだけど、ここまで暗くて救いのない世界観はシャレにならない。ブラックコメディといえども、ブラックの塩梅がちと強すぎる。現実の世知辛い世の中は、普通に生きているだけでも悲惨でコメディのよう。この残酷な寓話は、いま生きる現実に近すぎる。ヨルゴス・ランティモスの着眼点は嫌いじゃないけれど、ここまで暗いと、観た方も鬱になってしまう。なんだか他の作品も観るのが怖くなってきた。『哀れなるものたち』鑑賞へのハードルが一気に上がってしまう。
ある程度の心構えの上、やっぱり『哀れなるものたち』を観てみることにした。映画は確かにフェミニズムを描いてはいるものの、女性だけの生きづらさにフォーカスを絞ってはいない。登場人物たちはみな、不幸な生い立ちを持つ哀れなるものたちばかり。原題の『POOR THINGS』が示す通り、人権を奪われて生きてきた人たちが、自身の尊厳や愛について考え始める。毎回洋画作品の日本公開において、邦題のセンスの悪さに悩まされるが、この『哀れなるものたち』というタイトルはかなり良い。『ものたち』が『者たち』になっては意味が変わってしまう。まさに絶妙。
この映画を観ていて真っ先に思い出したのは、ダニエル・キイスの小説『アルジャーノンに花束を』と、メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』。フランケンシュタインについては作品だけではなく、作者のメアリー・シェリーの人生も参考にされている。『フランケンシュタイン』は、今から200年前の作品。当時のイギリスには女性の人権は殆どなく、女性名義で作品を発表するなどもってのほか。夫の名前でこの小説を世に発表していた。才女が活躍していくようになるという、フェミニズムの黎明作品でもある。
『アルジャーノンに花束を』も『フランケンシュタイン』も、主人公はもともと白痴で、急激に知性を身につけていく物語。彼らは自身の知性と外見との乖離で苦しむこととなる。作品の顛末としては、知性なんてない方が幸せなのではという着地点に到達していく。なんともやるせない。実際、いろいろ考えて生きていくことはとても辛いこと。ものごとをシンプルに捉えている方がどんなに生きやすいことか。でも、今回の『哀れなるものたち』は、知性があるからこそ幸せになれるということをシミュレーションしてくれている。主人公のベラは、ラストシーンも読書を楽しんでいる。
エマ・ストーン演じる主人公・ベラは、成人女性の身体に赤ん坊の脳を移植された人造人間。肉体は大人でも、精神は子ども。人は見た目が9割。その見た目に精神年齢も合わせようと、急激に成長を遂げる姿を描いている。純真無垢なベラが、自分を取り巻く世界に興味を示して、どんどん行動していく。彼女がひとつひとつ人生の扉を開いていく姿が小気味いい。そこは映画としての見せ場でもあり、とても楽しかったりもする。ただ社会というものは、正直に生きているだけでは怪我をさせられる。無防備に生きる人を利用したり、搾取しようとしたりする魔手や誘惑は、黙っていても迫ってくる。ベラは無傷ではいられない。
見た目は魅力的な女性で精神は子どもとなれば、男たちの征服欲に火が灯る。ベラの周りの男たちは、いっけん彼女の性的魅力に惹かされているように見えるが、実はそうではない。男たちも不幸な生い立ちを持っている。弱き哀れなるものたちは、自分よりも弱き存在を見つけ、服従させようとする。痴漢の加害者の動機が、性欲ではなく支配欲からくるものだとよく聞く。日々会社や家庭で、巨大な圧力に耐えている人物が、痴漢行為の加害者になりやすい。ここにも生きづらい哀れなるものたちの構図がある。
ベラは好奇心旺盛な人。興味のあることは、やってみなければ気が済まない。どんなに危険な匂いを感じ取っても、興味が湧いたらわざわざ自分からその荒海に飛び込んでしまう。そんな無茶ばかりしていると、いつか命を落としてしまうだろう。でもそんなアグレシッブさが、ベラを主人公とさせる所以でもある。
人は若い頃こそ怖いもの知らずで、身の丈以上のことを成し遂げてしまったりもする。もちろん逆に淘汰されてしまうこともある。人生経験を積んで、それなりに怖いものを知っていくと、いざというときに動けなくなってきてしまう。ときには命知らずのチャレンジ精神も必要。でもやっぱりベラの挑戦は無謀すぎる。彼女はこの冒険の旅を通して、心身ともにボロボロになっていく。
我々観客は、危険な冒険に挑んでいく主人公が大好きだ。それを自分に当てはめたら、絶対にこなせないことも知っている。だから物語の主人公に自分の成し遂げられない夢を託す。ベラの冒険は、我々が人生の道を踏み外さないための肩代わりでもある。「やりたいことはなんでもやってみろ」というのは乱暴な意見。やったら大怪我をするようなことは初めからしない想像力も身につける。『哀れなるものたち』は、衝動的な主人公の姿を通して、何でもかんでも挑戦すればいいものではないことを考えさせられる。
この映画は今時珍しくなってきたフィルムによる撮影をしている。画面にあるザラつきが懐かしい。あえて難しいフィルムによる撮影方法にも意味がある。この映画はリアルさを追求する作品ではない。すべてがベラの心象風景。作品の舞台もいつの時代なのかよくわからない。ロードムービーではあるものの、実際のその土地へ行ってロケーション撮影をするのではなく、大掛かりなセットを組んで、実際にはあり得ない風景をつくりだす。映画制作の手間や経費を、スタジオ撮影にかけている。
ベラの人生は陰惨で、そのまま描いてしまったら暗く重いだけのものになってしまう。刺激的な描写も多い。それらをオブラートに包むためにも、ファンタジー映画のような装いが必要となる。
映画はあくまでベラの視点で描かれている。色彩も、ベラがものごころをつくまではモノクロで、彼女が自分の意思で動き始めると、暖色の色鮮やかなカラーとなる。そしてベラが去った後の景色は、寒色で寒々しいものとなる。後半になるにつれ、ベラの知性が定着し始めると、画面は豊かすぎるくらいの現実的な色彩に落ち着いていく。
ベラを創り育てたマッドサイエンティストのゴッドウィン。彼自身も親である学者の実験体として、すでに身体はボロボロにされている。ゴッドウィンもDVの被害者で、彼もまた哀れなるもののひとり。DVを受けた子どもは、自分が親になったとき、自分の子どもにもDVをしてしまうとよく言われる。被害者が加害者に育っていってしまう構図。ゴッドウィンもずっと誰かを支配したかった。ベラが去った後、新たな人造人間を創るが、ベラのようには育ってくれない。たとえ人造人間であれど、生き物である限り個性が生じてくる。ゴッドウィンは、支配者になることを諦めたことで、人間らしく死んでいく可能性も生まれてくる。自分が「こうあるべき」と思い込んできたものを捨てたとき、初めて得られるものもある。
好奇心旺盛のベラは本を読むことが好きになる。支配者からすると、頭が良くなっていく人は厄介だ。ベラが社会主義に傾倒していくのも興味深い。資本主義は向上を目指していく思想。誰かが上を目指して獲得していくその過程には、踏み台にされていく多くの人々の苦しみが見えてくる。
資本主義の成功は、格差社会の確立の姿でもある。それは現代の社会情勢のリアルな姿。でも、社会主義を推して失敗した国の姿も近代史で我々は現実に見ている。どの思想が正しいと言い切れるものではない。ただこの作品では、人を支配しようとした者たちはみな失脚し、上もなく下もなく平等に生きていこうと決めた者たちは幸せそうに暮らして物語が終わる。それはこの物語の中の法則。
いろんなことに身をもって挑戦していくベラ。エマ・ストーンが演じるその人は、いつも不安そうで泣きそうな顔をしている。彼女はいつも怖がっている。それでも前へ進むしか選択肢がない。哀れなるものは、そこから這い上がるしかないのだから。
|
|
|
|
関連記事
-

-
『ツイスター』 エンタメが愛した数式
2024年の夏、前作から18年経ってシリーズ最新作『ツイスターズ』が発表された。そういえば前作の
-

-
『イレイザーヘッド』 狂気は日常のすぐそばに
渋谷のシネマライズが閉館した。自分が10代の頃からあしげく通っていた映画館。そういえば最近、
-

-
『トップガン マーヴェリック』 マッチョを超えていけ
映画『トップガン』は自分にとってはとても思い出深い映画。映画好きになるきっかけになった作品。
-

-
『スター・ウォーズ 最後のジェダイ』 特別な存在にならないという生き方
立川シネマシティ[/caption] 世界中の映画ファンの多くが楽しみにしていた『スター・ウ
-

-
『すずめの戸締り』 結局自分を救えるのは自分でしかない
新海誠監督の最新作『すずめの戸締り』を配信でやっと観た。この映画は日本公開の時点で、世界19
-

-
『エリン・ブロコビッチ』シングルマザーに将来はないのか?
日本の6人に1人が貧困家庭の子どもだそうです。 先日テレビで特集が再放送されて
-

-
『アンブロークン 不屈の男』 昔の日本のアニメをみるような戦争映画
ハリウッド女優のアンジェリーナ・ジョリーが監督する戦争映画『アンブロークン』。日本公開前に、
-

-
『オオカミの家』考察ブームの追い風に乗って
話題になっていたチリの人形アニメ『オオカミの家』をやっと観た。人形アニメといえばチェコのヤン
-

-
『たかが世界の終わり』 さらに新しい恐るべき子ども
グザヴィエ・ドラン監督の名前は、よくクリエーターの中で名前が出てくる。ミュージシャンの牛尾憲
-

-
『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』 あらかじめ出会わない人たち
毎年年末になるとSNSでは、今年のマイ・ベスト10映画を多くの人が発表している。すでに観てい




![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3c46b460.27499cf3.3c46b461.f86c602e/?me_id=1285657&item_id=11295721&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F00602%2Fbk4150413339.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3b7e64dd.cf47360e.3b7e64de.852c2549/?me_id=1213310&item_id=13980518&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2163%2F9784334752163.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)




