『Ryuichi Sakamoto | Playing the Orchestra 2014』 坂本龍一、アーティストがコンテンツになるとき
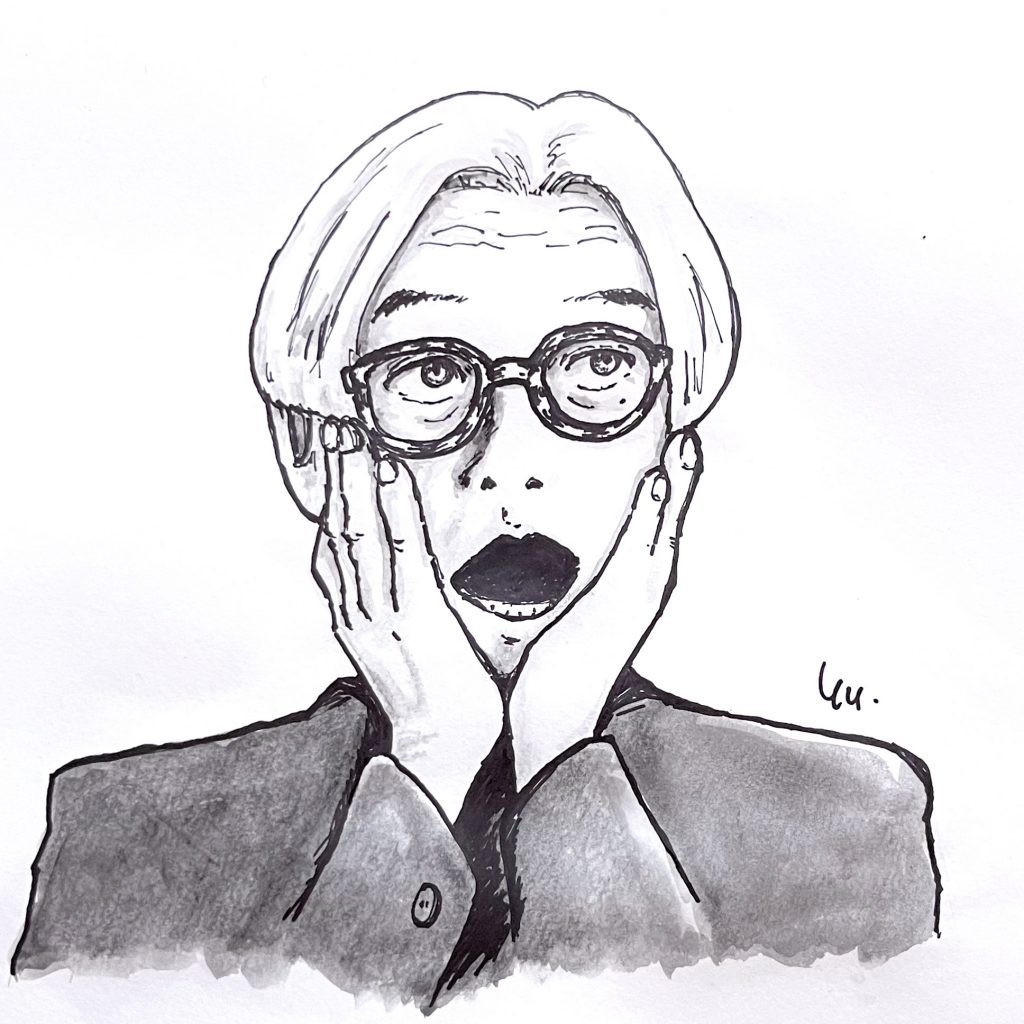
今年の正月は坂本龍一ざんまいだった。1月2日には、そのとき東京都現代美術館で開催されていた『坂本龍一 | 音を視る 時を聴く』展覧会へ行った。1月3日は、その流れでその日公開のライブ映画『Ryuichi Sakamoto | Playing the Orchestra 2014』を観に行った。
自分はSNSでは個人名をあげるときはいつも「さん」付けで呼んでいる。海外の人物ならば呼び捨てているが、国内の人なら、ご本人の目に入ってしまうかもしれない。失礼がないように敬称をつけている。でもなんだかここまで好きな坂本龍一を、他人行儀に「さん」付けで呼ぶのは照れ臭い。かと言って彼のニックネームである「教授」と呼ぶのも、普段から言っていないので違和感がある。今回は敬称略で進めていこう。自分は大の坂本龍一ファン。推し活なんて言葉がなかった1980年代のころからずっと聴いている。そのころ自分はまだ小学生だった。自分の人生のほとんどで坂本龍一の音楽がかかっていた。
日常生活でのものごとの物差しが坂本龍一基準になっていることにふと気づく。困ったオタク脳の仕様。たとえば自分に第二子が生まれるとき、出産予定日が1月17日だと聞くと、「すごい、坂本龍一と同じ誕生日になる!」と真っ先に頭に浮かぶ。(結果的に別の日になった。)また、パパ友のお子さんが、新宿高校に受かったと聞いたら「すごい、坂本龍一と同じ学校じゃない!」と開口一番に言ってしまう。優秀な成績を褒めるというよりは、坂本龍一と母校が同じなのが羨ましいという捉え方。嗚呼なんという視野の狭さ。そしてまた、あらためて坂本龍一は勉強ができたのだなぁともしみじみ感じる。
今回は映画『Ryuichi Sakamoto | Playing the Orchestra 2014』と展覧会『坂本龍一 | 音を視る 時を聴く』の話をしたいと思う。まずは映画の方から。
この映画はそもそもWOWOWで放送したもの。しかも放送当時は、コンサート会場から生中継だった。実は自分はこのコンサートツアーの別の日、別の会場でこのライブを実際に鑑賞している。自分が行った公演は、このとき新曲で初演奏だった『Blu』のPVの収録もするとのことだった。もしかしたら自分も画面に写るのではと緊張したが、もちろん写っているはずもない。そのとき生演奏で聴いた『戦場のメリークリスマス』のピアノは、とても力強い音だった。
後日放送のWOWOWでの生中継もリアタイで観ていた。まだ実際の演奏を間近に見た後の興奮冷めやらじの中継。のちに発表された、この模様を収録したライブアルバムもさんざん聴いていた。今回の映画版の大きな違いは、5.1chにサウンドリニューアルされているということ。ものすごく派手にリミックスされている。音楽を聴くにはかなりベストな状態。現場で生演奏と、CDの録音音源になったもの、今回の映画用リミックス版。どれもが印象がまるで違う。それらを聴き比べることができたというのも貴重な体験。不思議なもので、生演奏の音がいちばん地味な印象がしている。今回の映画版サウンドはとにかく盛りに盛られた印象で、エンターテイメント色がかなり強くなっている。本人が亡くなって、新たにファンになった人たちに対するアーティスト紹介も兼ねているのだろう。MCに英語字幕が付いているのも、世界でこれからこの映画を観る人もいるのだなぁと思わせる。
そういえばこのライブのときのMCで、坂本龍一さんが「今回ぎりぎりまでオーケストレーションしてて間に合わなかった曲があってね」と言っていた。「古い曲なんだけど」と『東風』のフレーズを弾いてくれた。「来年には間に合わせるから、楽しみにしててね」とも言っていた。このライブは2014年の4月に行われた。2014年の年末に、坂本龍一さんからは、癌による闘病開始で活動中止が発表される。あのとき予告されていた『東風』のオーケストラバージョンは、結局聴くことが出来なかった。
映画『Ryuichi Sakamoto | Playing the Orchestra 2014』は、本来は映画用に撮影されたものではない。すでに別編集のDVDも発売されている。その前年に亡くなる前の最後の記録として撮影された『Ryuichi Sakamoto | Opus』が世界的に話題になったのに便乗して、この過去のライブ映像を映画版にブラッシュアップしたものが公開される。『opus』には作家の意図はあるけれど、『playing the orchestra 2014』には作者の断りはない。本人が亡くなったことでの再評価に乗ったビジネス。アートというよりはタレントの売り込みといったところ。まさに商業芸術の矛盾。
『playing the orchestra 2014』を観にきた客層が気になる。映画館に来ている観客を見渡すと、結構お年を召したお客さんばかり。坂本龍一ファンのリアタイ世代が、単純に歳をとっただけかもしれない。でもやっぱり坂本龍一生前と没後では、客層が変わったような気がする。坂本龍一のファンというと、ものすごいオシャレな人か、強烈なオタクかに別れている。自分は明らかに後者。
坂本龍一生前と没後では、客層が変わってしまった現実は、展覧会『坂本龍一 | 音を視る 時を聴く』でも顕著に感じられた。年齢層が高いとばかり思っていたが、自分の子どもに近い若い層のお客さんも多い。ただ、美術館に来る客層の雰囲気ともちょっと違っている。もっとラフな感じ。坂本龍一が亡くなったことをきっかけに、新規ファンになった人も多いのだろう。ただSNSでは、この展覧会の大盛況の混雑で、人の多さを嘆く声が散見された。
どんなファンダムにおいても新規ファンと古参ファンとの軋轢が問題となる。坂本龍一ファンは、数十年固定客ばかりだった。本人が亡くなるという一大事件で、新たに出会うファンだっている。そんな新しいファンと、古いファンとでは、坂本龍一に対するイメージもだいぶ違う。
とにかく死後の坂本龍一の宣伝のされ方が、神格化され過ぎるということは、古参にとっては違和感でしかない。本人の魅力で宣伝していくのがいちばんなのだが、なんだか大袈裟にレジェンド扱いしていて、見ているこちらも恥ずかしい。
これはひとりのアーティストの人間性で人を惹きつけるのではなく、ひとつの商品、コンテンツとして売り込まれているからにも思われる。古参として死後から大幅に変わったなと感じるのは、グッズがめちゃくちゃお高い値段に設定されていること。いくら坂本が好きでも、ここまで高額だと手も足も出ない。購買欲も冷めて、むしろすぐ購入を諦める決断がきっぱりできてしまう。ファンならどんな値段でも買うべきだと、それこそ古参ファンから怒られてしまいそう。でもそれこそがカモがネギ背負っているだけの状態。ファンの声が届けば、プロモーションは変わってくる。なんだか選挙で政治が変わるのと似ている。だからこそ声をあげたい。グッズはもっと手軽な価格設定に見直してもらいたいと。
坂本龍一の展覧会は、彼が関わったインスタレーションが元となっている。生前の坂本龍一の言葉はいつも難解で、何を言っているのかさっぱりわからない。子どものころは、いつか自分も大人になったら、坂本龍一が何を言っているのかわかるのだろうと思っていた。実際自分が大人になってみると、坂本の言葉はやっぱりわからない。もう頭のつくりが根本的に違い過ぎるのだ。坂本龍一は難解だからと、オタク街道まっしぐらに行ける精神的な隠れ蓑にもなっていった。
展覧会の作品は、映像や音響を使って自然を表現するものが多い。テクノロジーを駆使して、アナログなものを目指していく。それはかつて坂本龍一がYMOで目指した、コンピューターを使って生演奏っぽく聴かせる技術の追求にも近い。YMOは、民族音楽を電子音楽で表現するイノベーションがかっこよかった。それらはつくられた自然だから、現実よりも盛られて厳選されている。あたかも『ブレードランナー2049』に出てきた、現実にはもうない自然の風景をバーチャルに創り出すドリームデザイナーのように。
そういえばピアノの自動演奏に、生前の坂本龍一の映像をホログラムで映し出すインスタレーションがあった。ファンはそこで涙すると聞いていたが、自分はそうならなかった。外から聴こえてくるピアノの音で心構えはできていた。でもそのプログラムの会場に入った瞬間に背筋が凍った。半透明に映し出された坂本龍一が怖かった。自分の中ではすでに坂本龍一はこの世の人ではないと受け入れているのだと感じた。『ブレードランナー2049』の中で、エルビス・プレスリーのホログラム演奏が流れていたが、それと同じだと思ってしまった。坂本龍一は昔の第1作目の『ブレードランナー』を好んでいた。まさか坂本龍一自身も『ブレードランナー』のディストピアな世界観の一部になってしまうとは。本人が知ったら苦笑いしそう。

いちばん楽しかったのは、中谷芙二子さんとコラボした『霧の彫刻』。観客は実際に霧の中に入って、完全にホワイトアウトを体験する。最初はワクワクするのだが、視界が見えなくなるのでだんだん怖くなってくる。それが楽しい。そういえば白人の太ったおじさんが、なぜか自分の写真を撮りたがっていた。白人オタク男性は、東アジア人の憂いたオタク男子に憧れていると聞いたことがある。自分が男子というのは無理があるが、憂いているのは間違いない。もしかしたらそのおじさんに狙われているのかもしれない。ホワイトアウトに紛れて、速攻で会場から逃げ出した。まさに文字通りケムに巻いてやった。これもバーチャルだけでは絶対に体験できない出来事。

坂本龍一のファンは、オシャレさんにせよオタクにせよ、基本的にはみんなおとなしい人種。今回、坂本龍一展が好評すぎて、映えポイントとして、普段の客層とまったく違う人種がたくさん集まってしまった。自分が行ったときはそうでもなかったが、連日並んで1時間以上待たなければ入場できないとか。古参のファンはこの変化についていけずに傷ついてしまっている。坂本龍一が神格化されたのではなく、ひとつの商品に変わってしまったことにも寂しさを覚える。
坂本龍一の人気は、母国日本よりも海外の方が高いように感じる。台湾や中国、韓国の方がずっと先に回顧展を開催していた。坂本龍一さんも生前、日本ではなかなか自分の音楽以外の作品を扱ってくれないと嘆いていた。今回、亡くなったからこその話題性で催された日本での回顧展。かなり皮肉。そして今まで坂本龍一を聴いたことのない新規ファンが殺到している。ご本人がこの状況を知ったら、やっぱり苦笑いしそう。でもきっと坂本龍一さん本人も、この意図しなかった化学反応を楽しんでくれそう。
生前から坂本龍一を聴いていた自分のような古参ファンは、坂本龍一が完璧な人ではないことを重々知っている。わがままで怒りっぽかったり、とにかく女性との浮き名が後を経たない困った人なのも周知のこと。それも今芸能界のスキャンダルで賑わせているような、誰かの忖度で女性を上納するようなシステムに乗っかるのではなくて、本当に普通にモテている。坂本龍一は天才なのはもちろんだけど、とにかくかっこよかった。噂になった有名人も才女ばかり。坂本龍一が普通に女性にモテるのは至極当然と納得してしまう。
坂本龍一が人気があったのは、とにかく本人もフットワークが軽かったところにあるだろう。テクノポップで出てきたと思ったら、映画のサウンドトラックではオーケストレーションの曲もつくってしまう。ロックやJ-pop、歌謡曲もあればピアノ曲もある。晩年は音の響きを追求した実験的な音楽も発表している。素地がしっかりしているので、なんでも器用にこなしてしまう。それこそ誰かが集めた坂本龍一のプレイリストのラインナップは、ガタガタな曲の集合体となってしまうので、なかなか聴きづらい。まるで同じアーティストの作品集ではないかのような印象となる。選曲者のセンスで、いかようにも変幻自在となってしまう。坂本龍一を理屈で理解しようとすると、一気にわかりづらくなってしまう。ただ、彼の作品のルーツを知れば、案外シンプルだったりする。音楽だったらドビュッシーやバッハ、サティなどの影響を受けて、映画だとゴダールやタルコフスキー。とくにこの展覧会のモチーフにはタルコフスキーへのオマージュでふんだんに溢れている。
坂本龍一展には、意外と小さな子どもたちが会場に来ていた。親が坂本龍一のファンで、よくわからずに展覧会に連れてこられた子たちだろう。子どもたちは光のオブジェの真下に入り込んだり、霧の中できゃあきゃあ叫びながら飛び込んでいく。きっとこの子たちの楽しみ方が、もっとも正しい坂本龍一の楽しみ方なのだろう。

坂本龍一はなまじ頭がいいから、難しい言葉をよく使う。でも根底はかなりシンプルで、ほんとうに子どものような好奇心で、いろんなものにきゃあきゃあ言っていただけ。アーティストというのは、極端に明るいか暗い性格の人が多い。坂本龍一は絶対的に前者の部類。自分たちもしかめっつらをしないで、素直にきゃあきゃあ言った方が絶対楽しい。自分たちは、坂本龍一のそんなミーハーで変人なところも大好きだった。
実際、自分も霧の中飛び込んで、冬なのにずぶ濡れになってしまったのがいちばん楽しかった。こんなにテンションが上がったのは久しぶり。坂本龍一の楽しみ方はまだまだたくさんありそう。やっぱり坂本龍一は楽しくてかっこいい。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
関連記事
-

-
『スイス・アーミー・マン』笑うに笑えぬトンデモ・コメディ
インディペンデント作品は何が出てくるかわからないのが面白い。『スイス・アーミー・マン』は、無人島に一
-

-
『ブラック・レイン』 松田優作と内田裕也の世界
今日は松田優作さんの命日。 高校生の頃、映画『ブラックレイン』を観た。 大好きな『ブ
-

-
『すずめの戸締り』 結局自分を救えるのは自分でしかない
新海誠監督の最新作『すずめの戸締り』を配信でやっと観た。この映画は日本公開の時点で、世界19
-

-
『銀河鉄道の夜』デザインセンスは笑いのセンス
自分の子どもたちには、ある程度児童文学の常識的な知識は持っていて欲しい。マンガばかり読んでい
-

-
『シビル・ウォー アメリカ最後の日』 戦場のセンチメンタル
アメリカの独立系映画スタジオ・A24の作品で、同社ではかつてないほどの制作費がかかっていると
-

-
『ベルサイユのばら』ロックスターとしての自覚
「あ〜い〜、それは〜つよく〜」 自分が幼稚園に入るか入らないかの頃、宝塚歌劇団による『ベルサイユの
-

-
『龍の歯医者』 坂の上のエヴァ
コロナ禍緊急事態宣言中、ゴールデンウィーク中の昼間、NHK総合でアニメ『龍の歯医者』が放送さ
-

-
『ベルリン・天使の詩』 憧れのドイツカルチャー
昨年倒産したフランス映画社の代表的な作品。 東西の壁がまだあった頃のドイツ。ヴィム・ヴェン
-

-
『猿の惑星:聖戦記』SF映画というより戦争映画のパッチワーク
地味に展開しているリブート版『猿の惑星』。『猿の惑星:聖戦記』はそのシリーズ完結編で、オリジナル第1
-

-
マイケル・ジャクソン、ポップスターの孤独『スリラー』
去る6月25日はキング・オブ・ポップことマイケル・ジャクソンの命日でした。早いこ











