『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』 問題を乗り越えるテクニック

映画『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』は、日本公開当時に劇場で観た。アメリカの911同時多発テロで父親を亡くした少年オスカーの物語。彼が父の死を受け入れるまでを穏やかに描いている。
初めてこの映画を観た当時は、なんとなく政治的な作品なのだと思っていた。911のテロは、アメリカの他国への戦争行為への報復。一般市民も標的にされた。普段の日常が営まれている都会が、一瞬にして戦場になった。当日日本の23時台のニュースでは、この信じられない出来事を生放送で伝えていた。その画面の向こうの大惨事は、どこか他人事に思えて、映画のCGでも観ているかのようだった。実感のない現実というのは、この頃から既に始まっていた。
こんなことが起こるなんて、その国の政治が問題なのではないだろうかと、若かりし日の自分は思っていた。日本は戦争とは関係のない国だから大丈夫と安易に高を括っていた。残念ながら2022年の現在の日本は、さまざまな形で他国の戦争に介入してしまっている。もうどこの国から逆恨みされているかわからない。自分たちのような一般市民が、突然攻撃されることもあり得ないことではなくなった。そう捉えればこのテロの恐ろしさが、他人事ではなく身近に感じてくる。
911テロへの癒しがこの映画の最大のテーマではあるだろう。でもそれだけではなさそうだ。主人公のオスカー少年は発達障害という設定。そうなると作品の見え方が変わってくる。スティーブン・ダルドリー監督は、薄っぺらい映画は作らない。この映画が制作された2011年では、まだまだ社会では発達障害についての理解がなかった。ましてや911テロ当時の2001年では、アスペルガー症候群と呼称され、特殊な精神病のような印象だった。現在では発達障害は10人に1人とされている。診断されている人数がそれだから、隠れ発達障害はもっといるはず。「障害」という言葉が示すにしては人数の割合が多すぎる。もしかしたら左利きの人よりも、発達障害の人の割合の方が高いような気さえしてきてしまう。
大きな音や人の多いところが苦手なオスカー少年。不安になったとき、その気持ちを紛らわすための小道具として、いつもタンバリンを所持している。オスカーがタンバリンを振るときは、彼が不安なとき。緊迫感のある場面でも、画面上はユーモラスになる。オスカーくんいま不安なのねと、映像的にもわかりやすい小道具の演出。劇中でオスカーは、「アスペルガーの検査を受けたけど、診断がおりなかった」と言っている。テロで父を亡くして以来、彼の生きづらい特性は悪化している。今なら間違いなく発達障害の治療をしてあげたい状況。
オスカーは数字に強くて、絵を描いたりする表現が得意。でも他人と話すのが苦手。そんな彼の不得手を心配したトム・ハンクス演じる父親は、オスカーと宝探しゲームをしていた。人とコミュニケーションを交わす練習。父親が亡くなったことで中断されていたこのゲーム。亡き父が残したお宝を探しだすことで、ロードムービーが始まる。
旅の途中、「間借り人」と名乗る老人が旅の友となる。この老人、戦争のショックで言葉を話せなくなってしまったとのこと。発達障害の少年と、PTSDの老人の社会的弱者同士のコンビも微笑ましい。老人を演じるマックス・フォン・シドーがいい。いつもは威厳のあるカッコいい爺さん役が多いのに、なんともこのしょぼくれた感。あらためて役者さんの演技力を感じる。
大切な人を突然失うことは、誰にでもあり得る。少年は旅をして、同じ苦しみを抱く人は自分だけではないと知っていく。
映画は予定調和の解決や、御涙頂戴の展開にはけしてならない。曖昧なまま穏やかな救いみたいなものが静かに流れてくる。それだけでいい。ファンタジー性の高い物語でありながら、逆に実在した人物の話を聞いたようなリアリティすら感じさせる。
小さな個人の力ではどうしようもできない大きな厄災に出会ったとき、我々はどう対処していったらいいのだろう。答えは出さずに考えてみる。生きるための哲学。考えるきっかけを与えてくれる映画だった。
関連記事
-

-
現代のプリンセスはタイヘン!!『魔法にかけられて』
先日テレビで放送していた『魔法にかけられて』。 ディズニーが自社のプリンセスも
-

-
『日の名残り』 自分で考えない生き方
『日の名残り』の著者カズオ・イシグロがノーベル文学賞を受賞した。最近、この映画版の話をしてい
-

-
『ダンダダン』 古いサブカルネタで新感覚の萌えアニメ?
『ダンダダン』というタイトルのマンガがあると聞いて、昭和生まれの自分は、真っ先に演歌歌手の段
-

-
『とと姉ちゃん』心豊かな暮らしを
NHK朝の連続テレビ小説『とと姉ちゃん』が面白い。なんでも視聴率も記録更新しているらしい。たしかにこ
-

-
『M3GAN ミーガン 2.0』 ゆるぎないロボ愛よ永遠に
自分はSFが好き。友だちロボットのAIがバグって、人間を襲い出すSFホラー映画『ミーガン』はずっ
-

-
『このサイテーな世界の終わり』 老生か老衰か?
Netflixオリジナル・ドラマシリーズ『このサイテーな世界の終わり』。BTSのテテがこの作
-

-
『みんなのいえ』家づくりも命がけ
念願のマイホームを手に入れる。自分の土地を得て城を持つことを夢に描くのは、日本人
-

-
発信者がウソをついてたら?『告白』
中島哲也監督作品、湊かなえ著原作『告白』。この映画の演出のセンスの良さにシビレま
-

-
『父と暮らせば』生きている限り、幸せをめざさなければならない
今日、2014年8月6日は69回目の原爆の日。 毎年、この頃くらいは戦争と
-
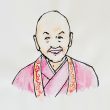
-
『死ぬってどういうことですか?』 寂聴さんとホリエモンの対談 水と油と思いきや
尊敬する瀬戸内寂聴さんと、 自分はちょっとニガテな ホリエモンこと堀江貴文さんの対談集





