『ブータン 山の教室』 世界一幸せな国から、ここではないどこかへ

世の中が殺伐としている。映画やアニメなどの創作作品も、エキセントリックで暴力的な題材ばかり。もっと心穏やかになれる場所はないだろうか。
昨年日本でも公開された『お坊さまと鉄砲』というタイトルの映画。なんだかその邦題だけでも、その映画を観たくなってしまう。なんでもブータンの映画とか。ブータンといえば世界でいちばん幸せな国として日本でも有名。国王夫妻が来日したときは、その可愛らしい夫妻のルックスに、日本人のほとんどが好感を抱いた。それから日本でもブータンという国を意識するようになった。ブータン国王夫妻の来日は2011年。もうだいぶ以前のこととなる。時の流れは早い。
『お坊さまと鉄砲』を演出したのはパオ・チョニン・ドルジ監督。その監督の前作にあたるのが『ブータン 山の教室』という映画。なんとも興味を惹かない地味な邦題。国際版の英題は『Lunana A YAK IN THE CLASSROOM』、和訳すれば『ルナナ:ヤクのいる教室』とでもなるか。原題は『ルナナ』とだけ。ルナナとは、ブータンでも人里離れた山奥の秘境にある村の名前。その実在している村を舞台にした映画が『ブータン 山の教室』。
殺伐とした現代社会に辟易していたところに、こんなのどかな映画が観たかったのだと食いついてしまう。世界でいちばん幸せな国の映画というだけで、とても興味深い。それこそ我が国日本で、幸せ指数の国民アンケートを取ったなら、幸せを感じていないと答える人が圧倒的に多くなってしまうだろう。世界的に見ても幸せを感じている国としては下の方。先進国ではたいてい最下位になってしまう。日本はそれほど幸せに暮らすには生きづらい国なのか。はたして幸せに生きるとは、いったいどういうことなのだろう。映画『ブータン 山の教室』に、幸せに生きるためのヒントがあるかもしれない。
主人公のウゲンは、教職免許こそはとったものの、その職業に嫌気がさしている。オーストラリアに移住して、歌手になる夢を抱いている。そんな現職にやる気のないウゲンに、山奥にある秘境の村の教師になれと、転属命令がくだされる。ウゲンは嫌々その村へ向かうこととなる。その村はルナナという。バスを乗り継ぎ、何日も山を越えて、やっと辿り着けるような辺境の地。当然電気や水道もない。Wi-Fiなんて届いてるはずもない。日本にあてはめるなら、100年前の生活を21世紀の現代でもやっているような場所。都会暮らしのウゲンが、帰りたい帰りたいと言いながら、ゆっくりと村に溶け込んでいく。
プロットだけ聞いてしまうと、かなり手垢のついた、ありきたりな物語に思えてしまう。そして観るものを必ず感動させてしまうような、御涙頂戴のあざとささえこの映画の企画には感じられてしまう。ただ、監督が1983年生まれの比較的若い、アーティスト肌の人だったおかげで、映画が浪花節にならないで済む。
主人公のウゲンは歌手志望。演じているシェラップ・ドルジも本業はミュージシャン。今回この映画が俳優デビュー作とか。ルナナ村での民謡とか、歌手志望の教師とか、音楽と密接な映画でもある。それでも映画は過剰な演出はしない。あくまで登場人物たちが口ずさむ歌だけが劇中音楽となり、ほとんどがルナナ村の環境音で構成されている。空気や風、草が揺れる音が全編に静かに流れている。主人公の教師ウゲンは、辺境の村に辿り着いても、地に足がつかず、いつもどこか遠くを見ている。あらかじめ別れが約束されている出会い。いくらでも叙情的に泣ける映画として、嫌味なくらい派手に描ける題材。盛ることなく、静かに淡々とカメラがルナナの村を捉えていく。その抑えた演出に好感を抱く。
登場人物たちもプロの俳優ではなく、実際にルナナに住む人たちをそのまま配役しているらしい。この映画に登場する人たちが醸し出す雰囲気は、つくりものではなく実際のもの。おおまかな脚本はあるのだろうけれど、この映画はほとんどドキュメンタリーに近いのだろう。とくに生徒役の9歳の女の子ペム・ザムがすごい。ルックスが華やかだから主役格に抜擢されたのだろう。自分はてっきりこの子は役者さんだと思っていた。なんでも現地の子をそのまま採用したとか。役名と役者の名前が同じなので、まさかとは思っていた。スタッフはものすごい逸材を見つけてしまった。この映画の成功は、ペム・ザムちゃんの存在感で決まった。あんなキラキラした目で、「先生!」と慕ってこられては、むげにできない。今すぐ帰りたい教師でも、このひとときだけは授業をしてあげようと思ってしまう。ここに登場する子たちが笑ったり泣いたりしている姿は、演技ではないのかもしれない。
映画は単純に物語を語るだけではない。ブータンという国を世界に紹介しようとする政治的な匂いも感じ取れる。プロパガンダ映画と言っては厳しいが、ブータンという国をあげて、この映画を世界標準に乗せようとしているのがわかる。それは主人公が、国策である国民総幸福政策のため、教師の職業は国の役に立てるありがたい仕事だと、あちこちで言われているところからも感じ取れる。
ブータンでは国民総生産量であるGNPの増大より、国民総幸福量のGNHの方が大切であると、国策として後者に力を入れている。厳密にいえば、ブータンが「世界でいちばん幸せな国」なのではなく、「世界でいちばん幸せな国を目指している国」と言った方がいい。
映画に登場する人たちはみな貧しい。舗装されていない山での生活なのに、靴も持っていない。水道がないので、トイレも不衛生。もし病気や怪我をしたら、すぐさま命の危険を感じてしまう。ライフラインが整っていない。主人公が住む首都のティンプーも、日本の過疎のようなところ。この映画の価値観からすると、都会の教師が辺境の村に赴任する姿として描かれているが、日本の視点からすると、田舎から原始時代へ向かうような印象まで受けてしまう。経済第一主義の現代の価値観には嫌気がするけれど、ルナナ村のような文明から隔離された社会で生きるには、現代人としてはかなり覚悟がいる。世界でいちばん幸福な国を目指すと国が言ってしまうのは、貧しさを克服できない国情への詭弁ではないかと邪推すらしてしまう。ウゲンでなくとも、ここではないどこかへ逃げ出したくなってしまう。
でも、この50人強しかいない小さな村では、教師のウゲンは貴重な存在。生徒のひとりは「教師は未来に触れる大事な仕事。自分も教師になりたい」と言う。これは大人の誰かから聞いた言葉の受け売りなのはわかる。言った本人がその言葉の意味を実感していない。ここで言われる「未来」は、未来へつながる子どもたちのこと。子どもからしてみれば、将来のある自分たち自身のこと。自分を「未来」と言ってしまっている気恥ずかしいパラドックス。
そんな小さな村では、ウゲンの居場所は容易に出来上がる。それでもウゲンのような若者は、世界を見るのも必要なこと。この小さな世界から飛び立てる切符があるのなら、旅に出ない理由もない。すでに居場所がルナナにできてしまいながらも、ここではないどこかへ行ってみたい。ここに残るか、都会に戻るか、それとも外の世界へ武者修行に行くか、ウゲンには選択肢がたくさんある。これはかなり幸せなこと。不幸というのは、生きる選択肢がないこと。外へ行けるけど、自分の意思で行かないなら、それは不幸ではない。
都会というのは人の心を荒ませる。自分も都心へ行って郊外へ戻って来ると、そこにいる人たちが優しい雰囲気にホッとする。さらに地方へ行けば、そこに住む人たちはさらに優しい雰囲気を醸し出している。信号のない道路を渡ろうと立っていると、車はすぐ止まって歩行者に譲ってくれる。それだけで驚いてしまう。なんて優しいの。そして地方から郊外へ戻ると、なんてギスギスしているのかとうんざりしてしまう。都心から郊外へ戻ったときは、優しく感じたのに。そうなるともう都会には戻れない。そんな自分の肌感覚からしても、きっとルナナの人たちが優しいのは想像がつく。地方から上京してきた人が、「若いときは都会で暮らすけど、いつかは故郷に戻るつもり」と言っているのをよく聞く。自分は関東生まれの関東育ちなので、いつか帰る場所があるのがうらやましく感じたことがある。
ルナナの学校で驚いたのは、授業が英語で行われているというところ。生徒の子どもたちは、普段はブータンの母国語であるゾンカ語で喋っている。それにも関わらず、ひとたび授業が始まるとみんな英語で喋り出す。みんながみんな流暢に英語を喋る。英語の歌だって、抵抗なく歌えちゃう。バイリンガルがデフォルトになっている。日本人のほとんどが日本語しか喋れないのに比べると、国民全員が世界標準語である英語が喋れるというだけで、教育に力を入れている国だとわかる。どんなに貧しい国情でも、教育には力を惜しまない。そこは日本と大きな違い。見習うべきポイント。ブータンもいつかは本当に「世界でいちばん幸せな国」になっていくことだろう。
さまざまな国の映画を観るのは楽しい。旅行では見えないその国の生活感も見えてくる。カルチャーが進んで、どの国の映画もハリウッドスタイルになりつつある。映画の表現方法が単一になってしまうのはつまらないけれど、そのおかげで、映画表現に世界共通の表現言語ができて、観やすくもなっている。それがいいことなのか悪いことなのかはわからない。だけどそのおかげで、どこの国の文化の映画が来ても、そこにいる人たちに感情移入できるようにもなってきている。よその国のよその文化圏でも、みな同じ人間。わけがわからないことは起こらない。世界の人々を知っていく手段として、映画鑑賞がひとつの方法にもなっていく。「世界でいちばん幸せな国」という言葉にも、いろいろな意味が含まれている。それを感じ取れただけでも、この映画を観た意味がある。ここではないどこかは、どこにもないしどこにでもあるということ。
映画『ブータン 山の教室』が製作されたのは2019年のコロナ禍前。日本公開は2021年。日本でのフラグシップ上映館は岩波ホールだった。岩波ホールは2022年に閉館となっている。コロナ禍での観客の不入のための閉館らしい。岩波ホールは、アート系作品を中心に上映していた単独系の映画館。このような個性的な映画館が、コロナ禍以降どんどん減っていってしまっている。それどころかシネコンですら、洋画の客入りが不振となってきている。
原因としては、配信で映画を観るのが主流となっているからだろう。コロナ禍でステイホームを国から言われて、することがなくなった人たちで、一気に配信文化が広まった。普段、映画などの映像コンテンツを観ない人ですら、サブスクで動画を観るようになってきた。それはそれで文化が栄えるので、まったく悪いことばかりではない。
ただ、映画館に人が行かなくなると、弱小の個人経営的な映画館は経営が厳しくなっていく。大企業が経営しているシネコンは生き残れるかも知れないけれど、それでは個性がなくなっていく。客が来なければ、入場料金も高くなっていく。そうなると尚更映画館へ客足が遠のいていく。ボタンを押せばすぐ映画が観れてしまう配信サービスの便利さは否めない。探せばたいてい観たい映画は見つかる。再生ボタンを押せば、すぐ映画が始まる。こちらの鑑賞への心の準備が、まだできていないのも関係なし。映画鑑賞がドライなものとなっていく。これも時代の流れ。受け入れるしかない。
ふとこのコロナ禍の時期、ルナナの村はどんな様子だったのだろうと、想像を膨らませる。世界の終わりかと思わされた厄災も、きっとあの村ではあまり影響がなかったかも知れない。あの村の子どもたちも、きっと大きくなっただろう。映画が終わったらそれですべてが完結しない映画は良い。映画の物語は終わるけど、登場した人々の人生はまだ続いていると感じさせる映画。『ブータン 山の教室』は、確かに幸せな映画なのかもしれない。
|
|
|
|
関連記事
-

-
『ワンダーウーマン』 女が腕力を身につけたら、男も戦争も不要となる?
ガル・ギャドットが演じるワンダーウーマンの立ち姿がとにかくカッコイイ! それを一見するだけで
-

-
『ブラック・クランズマン』明るい政治発言
アメリカではBlack Lives Matter運動が盛んになっている。警官による黒人男性に
-

-
『Ryuichi Sakamoto | Playing the Orchestra 2014』 坂本龍一、アーティストがコンテンツになるとき
今年の正月は坂本龍一ざんまいだった。1月2日には、そのとき東京都現代美術館で開催されていた『
-

-
『パンダコパンダ』自由と孤独を越えて
子どもたちが突然観たいと言い出した宮崎駿監督の過去作品『パンダコパンダ』。ジブリアニメが好きなウチの
-

-
『機動戦士ガンダム 水星の魔女』 カワイイガンダムの積年の呪い
アニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』が面白い。初期の『機動戦士ガンダム』は、自分は超どスト
-

-
『透明なゆりかご』 優しい誤解を選んでいく
NHKで放送していたドラマ『透明なゆりかご』。産婦人科が舞台の医療もの。これは御涙頂戴の典型
-

-
『Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022 +(プラス)』 推しは推せるときに推せ!
新宿に『東急歌舞伎町タワー』という新しい商業施設ができた。そこに東急系の
-
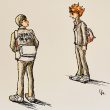
-
『ハイキュー‼︎』 勝ち負けよりも大事なこと
アニメ『ハイキュー‼︎』の存在を初めて意識したのは、くら寿司で食事していたとき。くら寿司と『
-

-
『プレデター バッドランド』 こんなかわいいSFアクション映画が観たかった
『プレデター』の最新作が公開される。近年日本では洋画が不人気。この『プレデター バッドランド
-

-
『プライベート・ライアン』 戦争の残虐性を疑似体験
討論好きなアメリカ人は、 時に加熱し過ぎてしまう事もしばしば。 ホントかウソかわから








