『ひとりでしにたい』 面倒なことに蓋をしない

カレー沢薫さん原作のマンガ『ひとりでしにたい』は、ネットでよく読んでいた。そもそもカレー沢薫さんを知ったのは、自身の発達障害の治療の様子をマンガにした『なおりはしないが、ましになる』を知ったのがきっかけ。SNSで誰かのつぶやきでこのマンガを紹介していて、そこから興味が湧いて読むようになっていた。マンガを読んでいると、カレー沢さんはかなり発達障害の症状で生きづらさを感じている。部屋を片付けるのが苦手だったりするくらいならいいが、日常のコミニュケーションに支障がでるくらいのスマホ依存症だったりする。編集の担当者の勧めで、治療を受けながら、それをエッセイマンガにしたらどうかとなった。実体験に基づくマンガなので、かなり説得力のあって読みごたえがある。
『なおりはしないが、ましになる』の冒頭で、主人公が検査を受けたら、発達障害の診断がでる場面がある。「こんな診断がおりた」と旦那さんに相談すると、「それで何か変わるの?」と質問される。「診断がおりたから、今日から何か変わるわけでもないし、今までの君でやってこれたのだから、これからもそんなに大きな変化はないんでしょ?」と返される。そもそもカレー沢さんの旦那さんは、変わった人であるカレー沢さんを面白いと思って付き合っている。彼女との日常で、困ったと感じることはあまりないのかもしれない。むしろカレー沢さん自身が、平生普段に生きづらさを感じていたのかもしれない。発達障害という診断がおりたなら、その病状はある程度ひな形にあてはまってくるので、それほど特異な存在ではなくなってくる。ひとつの病として対処していけばいい。発達障害は脳がもたらす特性なので、完全に治療することはできない。でも、人間関係に支障が出ないくらいの考え方は、認知行動療法でトレーニングできる。だからこそ『なおりはしないが、ましになる』ということ。病は本人が自覚して、始めて治療に取り組むことができる。自身の病を認めることが、治療の最大の壁なのかもしれない。
カレー沢薫さんの『なおりはしないが、ましになる』と同時進行で連載されていた『ひとりでしにたい』。すっかり社会福祉に詳しくなった作者が、ルポ作品ではなく、ストーリー展開で社会問題に斬り込んでいく。オタク気質のカレー沢さんの作風が、社会派の題材を描くのがいい。暗くて重い孤独死というテーマ。それを重くなりすぎない程度で、コメディとして描いていく。いつかは誰でも訪れる死については、気にはしているけれど目を背けたくなってしまう。もしかしたら今日、突然事故に遭って命を失うかもしれない。一日伸ばしにしたいテーマではあるが、その時が突然やって来て、慌ててしまわぬように心の準備もしておきたい。それは年齢を問わずに考えなければならない問題でもある。
よくこんな暗いテーマでマンガを描いたと、偉いなと感心してしまう。これこそ本当に知りたかったことだったりもする。物語の形をとって、この重苦しい問題をシミュレーションしていくのは清々しい。重いテーマをそのまま重く触れていくのではちっとも面白くない。そのまま暗く描く作品なら、今までもたくさんあった。そんなものなら観たくない。
主人公が独身中年女性ということ。世の中の価値観は急激に変わりつつあるが、まだまだ世間の風当たりは独り者や女性には厳しい。その理不尽な社会の目から導入していって、はたして結婚することが本当の幸せなのかという問いかけを投げかけてくる。これをやっておけば安泰という迷信を持ちたがるのは、同調圧力の強い日本人の国民性ゆえの価値観とも言える。でも慣例に沿って生きることが、必ずしも幸せとは限らない。人生観は人それぞれ。あの人にとっての幸せは、自分にとっては息苦しいものだったりもする。孤独死を通して、そうならないためにどうしたらいいかを考える。上手に死ぬにはどう生きたらいいか。死を考えることで、生き方について見つめ直させられる。もうこれは人生哲学。メメントモリ。
このマンガを読んでいて、これこそドラマ化したらいいのにと思っていた。でもこんな暗いテーマの作品、日本では絶対映像化されないだろうとも思っていた。それこそ数年前までの失われた30年では、不況なのにメディアはそれに蓋をしていた。そんな時代では、死をテーマにするようなシビアなテーマの映像作品など、企画の段階でNOが出ていた。明るく軽薄に、景気の良いふりをすることを求められていた。むしろ真摯なことをやろうすれば、冷笑される風潮すらあった。それがまさかの『ひとりでしにたい』のドラマ化実現。しかもNHKで。主人公の鳴海役はなんと綾瀬はるかさん。そのお母さんとお父さんは、松坂慶子さんと國村隼さんが演じてる。大河ドラマの俳優さんばかりの超メジャーキャスティング。しかも脚色は大森美香さん。大河ドラマや朝ドラの名脚本家。アングラっぽいカレー沢薫さんが、いきなりメインストリームに駆り出された。そういえばNHKの最近のドラマは、社会問題を題材にしたシビアな作品が多い。暗いテーマというだけで企画が通らない時代はもう終わった。
自分がシナリオライター養成学校へ通っていたとき、NHKのシナリオコンクールの説明会に行ったことがある。そのときの講師が大森美香さんだった。休憩時間、トイレの前でばったり大森美香さんと出くわしてしまった。自分と同年代の女性が、日本でトップクラスの脚本家として活躍している。同じ人間でも、さまざまな人生があるものだなぁと実感させられてしまった。本来なら関わることのない人同士が、そのとき偶然すれ違ったという感じ。
キャスティングといえば、主人公の鳴海さんが悪夢のような被害妄想に陥ったとき、心象風景に出てくる妖怪を麿赤兒さんが演じてる。古い映画ファンとしては、昭和のATGの映画をすぐ思い出してしまう。アングラもアートもインディーズもNHKドラマに大集結。ある意味、夢のようなスタッフキャストで制作されている。
マンガやアニメの実写化というと、原作を無視した映像化で、かえって原作に泥を塗るなんてこともよくある。あまりに原作を汚されて、追い詰められた原作者が自死してしまうなんて事件もあった。もし『ひとりでしにたい』の企画も、「こんな暗いテーマの作品、そのまま映像化できないよ」とアホなことを言うプロデューサーがいたら、すべては台無しになってしまう。今回のドラマ化は俄然期待していたが、よくある失敗の映像化になったら、すぐさま視聴をやめるつもりだった。第一話は、原作ではさらっと触れている主人公の設定も、韓国ドラマのような脚色で掘り下げられている。本題になかなか入らないのはまどろっこしいが、この説明はドラマには必要なのかもしれない。鳴海さんが推し活している設定も深掘りしている。鳴海さんが推しているのは、日本のアイドルの設定になっているが、このファンダム文化の描写は、K-POPのそれ。大森美香さんかブレーンのスタッフの誰かが、かなり韓流カルチャーに造詣が深いようだ。原作にはない深掘り設定で、推し活描写にリアリティが出てくる。作品のギミックである推し活文化も、実は生きるためには必要不可欠なものと作中でも言っている。夢中になるものがあるというのは、それだけで希望につながる。人が人らしく生きていくには希望が絶対不可欠。
「健康で文化的な最低限度の生活」とかいう、なんだか嫌な響きの言葉がある。生活保護に関わる言葉だが、そこでは趣味などは生きていくには無用とされている。国から生活費を支給されているのだから、趣味など許されるわけがないということ。でもそれならその人は、ただ生きているだけになってしまう。仮に、最低限生きるだけの生活費が得られたとしても、それだけではその人は充分に生きているとはいえない。最低限度の生活を目指しているだけでは、最低以下の生活しか保てない。もちろんそこから抜け出す胆力すら培えない。人生には楽しみが持てる余裕が必要。人は心から先に死んでいく。
主人公の鳴海さんは、自分の趣味の推し活グッズで、勤務先のデスクも埋め尽くしている。あまりにオープン過ぎて、プライベートが社内にダダ漏れ。これは原作にはない鳴海さんの描写。鳴海さんは孤独死が嫌なので、慌てて婚活を始める。そこで初めて独身中年女性が婚活をすると、それだけで舐められるということを知る。そもそも大らか過ぎる鳴海さんの性格は隙だらけ。他人から舐められる要素が多過ぎる。でもそのおかげで、他人と接する機会もできてくる。ドラマとしてはそれで話が自然な流れで展開して行ける。要するに鳴海さんは、周りがほっとけなくなってしまう人。これも人徳と言えるだろう。
思えば自分も勤務先では、自分の趣味は完全にシャットダウンしている。あたかも無趣味でございますとしていた方が、仕事がやりやすいということに気づいてしまったので仕方がない。たとえ誰かと趣味が同じだとしても、必ずしもその人と性格が合うとは限らない。自分の趣味は映画だが、もし映画ファンの上司や先輩がいたとして、はたして映画の話題で盛り上がるとは到底思えない。目上の人に「こいつとは映画の話ができる」と思われてしまうと、一方的にその話をされて、本来やらなければならない仕事に支障が出てしまうことにもなりかねない。相手が上司なら、無碍にすることも難しい。そんな煩わしい立場にならないためにも、自分のプライベートに関わる情報は、オフィシャルの場である会社ではひた隠しにしておいた方が面倒が起きにくい。最低限のリスクヘッジ。哀しい処世術。だからこそみんな、ネット上で趣味の話をするようになってきたのだろう。かつて職場では、政治と宗教の話はタブーとされていた。いつしかスポーツの話もトラブルになりがちなので、あまりしなくなってきた。同じスポーツファンでも、推しが競合チームだった場合は、試合の結果でかなり気を使わなけれはならなくなる。職場では仕事以外のストレスはなるべく避けたい。世知辛い考え方だけど、それもこれも忙し過ぎて貧しい日本社会が原因と思われる。趣味の話も気楽にできないほど、日本は景気が悪いということか。
自分がいつかは死んでいくことは当たり前のこと。でもなんだか怖くてそのことに蓋をしてしまう。見てみぬふりをし続ける。それを避ければ避けるほど、死に対して怖さが増幅していく。
コロナ禍のとき、未曾有の疫病に自分たちは恐れ慄いた。このままみんな死んでしまうのではないかと、パニックやヒステリックになっていった。ネットでもデマが蔓延って、恐怖を煽動する話題が拡散されてくる。そんな中、哲学者や社会学者のような知識人の言葉の発信がとても心強かった。彼らの発する言葉は冷静で、まるでこの不安な状況下ではないかのようだった。なぜこの人たちはこんなに冷静でいられるのだろう。今でこそ、あのコロナ禍の頃の不安な気持ちをほとんどの人が忘れてしまったけれど、あの緊張した社会状況のなかで発せられた言葉を、今読み返してみても勇気づけられてしまう。その言葉を発している人だって、いつ自分もコロナに感染して、命の危機に晒されるかもしれないというのに。
ものごとには、知らないからこそ余計に怖いということがある。世の中にある差別や戦争は、無知から生まれてくることがほとんど。正しく知って、正しく怖がることを賢者たちは言っていた。『ひとりでしにたい』を観ていると、死というものはけっして遠い存在ではなく、とても身近な出来事だと知ることができる。避けられない道ならば、知っておいた方が怖さが減っていい。マンガやドラマは、現実逃避の媒体ではあるけれど、『ひとりでしにたい』では、現実をズバリ突きつけてくる興味深い作品になっている。ここで語られる話は、なにも目新しいものではない。少し調べればわかることだけれど、調べなければ永遠にわからないままのことでもある。いざとなったときの社会保障は、日本は案外整っていたりする。でも調べて申請しなければ、その制度にもたどり着くことはない。面倒だからこそ、こんなマンガやドラマで啓蒙されていくのもいい。臭いものに蓋をしてしまうと、中でどんどん腐っていってしまう。いざ蓋を開けたときにとんでもないことになりかねない。臭いものは早いうちに片付けて、整理整頓しておいた方がストレス回避となる。人生の大事なことは、たいていめんどくさい。そしていっけん、些細で他愛ないもののように見えている。
ドラマを通して死を見つめることで、自分の人生に向き合ってみるきっかけを与えてもらった。このドラマでは、くだらないことをやってるようでいて、自分の人生観にちょっと影響を与えてくれるものがすこしある。軽くて重い、良い塩梅のドラマ。原作はまだ続いているので、ぜひともドラマ版も続きをつくって欲しい。まだまだ語るべき些細で他愛ない問題は、たくさんあると思われるから。
|
|
|
|
|
|
関連記事
-

-
『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』 日本ブームは来てるのか?
アメリカで、任天堂のゲーム『スーパーマリオブラザーズ』を原作にしたCGアニメが大ヒット。20
-

-
映画づくりの新しいカタチ『この世界の片隅に』
クラウドファンディング。最近多くのクリエーター達がこのシステムを活用している。ネ
-

-
『やさしい本泥棒』子どもも観れる戦争映画
人から勧められた映画『やさしい本泥棒』。DVDのジャケットは、本を抱えた少女のビジュアル。自分は萌え
-

-
『ベイビー・ドライバー』 古さと新しさと遊び心
ミュージカル版アクション映画と言われた『ベイビー・ドライバー』。観た人誰もがべた褒めどころか
-

-
高田純次さんに学ぶ処世術『適当教典』
日本人は「きまじめ」だけど「ふまじめ」。 決められたことや、過酷な仕事でも
-

-
『うつヌケ』ゴーストの囁きに耳を傾けて
春まっさかり。日々暖かくなってきて、気持ちがいい。でもこの春先の時季になると、ひ
-

-
夢は必ず叶う!!『THE WINDS OF GOD』
俳優の今井雅之さんが5月28日に亡くなりました。 ご自身の作演出主演のライ
-

-
『ダンダダン』 古いサブカルネタで新感覚の萌えアニメ?
『ダンダダン』というタイトルのマンガがあると聞いて、昭和生まれの自分は、真っ先に演歌歌手の段
-
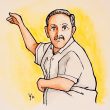
-
『髪結いの亭主』 夢の時間、行間の現実
映画『髪結いの亭主』が日本で公開されたのは1991年。渋谷の道玄坂にある、アートを主に扱う商
-

-
『はじまりのうた』 音楽は人生の潤滑油
この『はじまりのうた』は、自分の周りでも評判が良く、とても気になっていた。当初は「どうせオシ









