『舟を編む』 生きづらさのその先
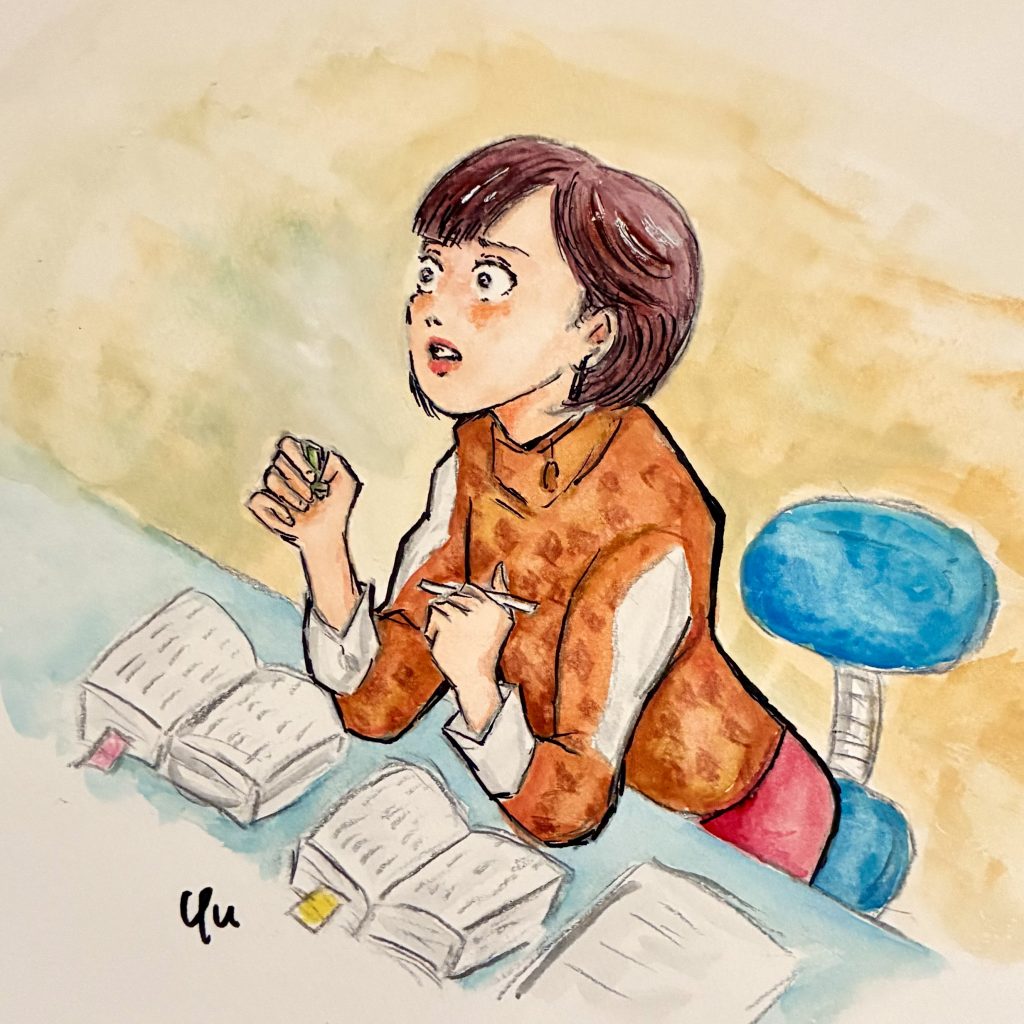
三浦しをんさんの小説『舟を編む』は、ときどき日常でも話題にあがる。松田龍平さんと宮崎あおいさん主演の映画も「おもしろいよ」とよく聴く。いつかは観たい作品だとは思っていたが、なかなか観るきっかけがなかった。2025年の6月、この『舟を編む』のドラマ版がNHKで放送された。昨年の2024年にNHK BSで放送されたものの地上波放送とのこと。このドラマ版から最初に観ていくことにした。
『舟を編む』は、辞書制作に携わる人々を描く職業紹介もののジャンルにあたる。自分の知らない仕事を、物語を通して教えてもらえるこの手のジャンルは、とても興味深い。辞書という、生活にあって当たり前で、普段あまり意識しないものをつくっている人たちの姿。ちょっと考えれば、この辞書という書物だって、誰かが文章を考えて書いていることはわかる。でもそれがどんな人がどうやってつくっているかを想像することはほとんどない。でも辞書を引くときは、やっぱり博識な誰かに質問しているような気持ちになっているのは確か。辞書制作は本当にごく少人数の人たちでつくられているのは想像がつく。どんな人がどんな想いでこの「辞書」という書物に取り組んでいるのか。知的好奇心が刺激される。
ドラマ版の1話を観ておもしろいと思ったので、すぐさまその先の展開が知りたくなった。せっかちな自分は、物語の全体を2時間で見渡せる映画版を観てみることにした。でも、あれ? 映画版にはドラマ版の主人公・岸辺みどりが出てこない。それどころか岸辺さんの上司・真締(まじめ)さんすら出てこない。辞書編集部のおじさんたちが、自分の後進について話し合っている。え、真締さんもまだ辞書編集部に在籍していないの。ドラマ版では辞書編集部の上長となっている真締さん。劇中では辞書づくりに15年くらいは平気でかかると言っていた。そうなると、この映画版はドラマ版の15年くらい前ということになる。ようするにドラマ版からすれば、映画版はエピソードゼロということになる。なんだかまどろっこしい。
慌てて原作小説を読み始める。映画版は原作に近い映像化作品。ドラマ版は大胆解釈で、主人公も変えてしまっている。映画版で映像化されてなかった部分から作品に斬り込んでいるユニークな語り口。ドラマ版の主人公は池田エライザさんが演じる新人編集部員の岸辺さん。映画版では黒木華さんが演じているけど、そちらではほとんど出番がない。映画版だけを観た人からすれば、「そんな人いたっけ?」というくらい存在感が薄い。映画版も原作も主人公は真締さんとなっている。映画版では松田龍平さんが演じてドラマ版ではRADWIMPSの野田洋次郎さんが演じている。どちらもハマり役。原作では岸辺さんは中盤の語り部となる。原作小説の主人公は基本的には真締さんだけれど、視点を変えるような形で、中途参加の岸辺さんにバトンタッチするかのように主人公が切り替わる。仕事も家庭も手に入れた真締さんを客観的に見る手法。この小説の語り口も面白い。そういえばこの作品はアニメ版もある。キャラクターデザインがイケメンすぎて、それはそれで違和感がある。今度こちらもゆっくり観てみよう。
ドラマ版と映画版、主人公も変わっているので、作品のテーマも違ってきている。映画が2013年の作品なので、この物語にかかった辞書制作の時間そのままの時間軸が過ぎていることになる。俳優こそ変わっているが、そのまま時間が過ぎているような不思議な感覚。原作の持つテーマは、辞書づくりに携わる職人気質の人たちの思考や行動の面白さを、敬意を評しながら描いている。映画はその変わった人ですら恋をするのだと、恋愛にスポットをあてている。たくさん物語が紡がれている現代では、むしろ恋愛物語ほど陳腐な題材はない。ただ恋愛は誰でも理解できる感情だし、人生において重要なイベントでもある。万人に作品を訴えかける取り掛かりとしては、扱いやすいテーマでもある。ストイックな研究者であり、変人でもある真締さんが恋をする。これはこれでかなり興味深い。
かつてオタク系やおとなしい男性のこと「草食系男子」と呼ぶことがあった。恋愛に積極的な男性を「肉食系」と言っていたので、その反意語の言葉。この言葉が使われていた15年くらい前までは、まだバブル期の名残もあって、貪欲なくらい積極的で上昇気性の人の方が認められていた。今となっては、そんな勢いだけでは人生はやっていけないことは誰もが知っている。「草食系男子」が蔑称だった時代でも、「自分は草食系男子の方が結婚相手には良い」と言っている女性は少数派ながらいた。草食系の人はたいてい趣味があるので、寄り道しないで毎日帰ってくるし、ギャンブルなんて不確かな遊びはしない。当然浮気なんかするはずもない。当時はちょいワル肉食系男子全盛の時代だったが、現代では草食系男子の方がデフォルトのような感じがする。だからこそ「草食系男子」という言葉が廃れていったのかもしれない。
今でこそ真締さんは発達障害のASDなのがわかる。発達障害の生きづらさは、こだわりの強さからくる頑固さにある。作中でも言っているが、現在世間に流布している「こだわり」という言葉の意味は、本来の意味とは違ってきたものらしい。「職人のこだわり」とか広告のキャッチコピーで使われたのをきっかけに、「こだわり」という言葉は良い意味のように使われ始めてしまった。本来の「こだわり」はけっして良い意味で使われていなかった。そもそも「こだわり」は、それを持つ人を生きづらくさせるもの。真締さんが魅力的なのは、ASD的なこだわりをもちながら、人の意見を聴ける柔軟性も持っているところ。そしてその特性は、辞書づくりにぴったりだったということ。
発達障害の生きづらさを抱えた人でも、自分に合う環境にいられたら、その特性の短所は治ってくるという。ドラマ版は辞書づくりが最後の佳境に差し掛かる頃の話。真締さんは自分の能力が充分に活かせる環境に身を置き、安心して心を委ねられるパートナーも側にいる。原作では岸辺さんも同僚の西岡さんも、真締さんに嫉妬心すら抱いている。あんなに変な人なのに、人生で欲しいものをぜんぶ手に入れている。勝ち組じゃないかと。
新人の岸辺さんの視点で描かれるドラマ版は、恋愛要素が強い。自分の周りでは「恋愛ものは苦手」という人は多い。人生の中に恋愛があるのは当然だが、それだけがメインの物語はかなりつまらない。岸辺さんは恋愛気質の人。いわゆる「肉食系女子」にあたる。池田エライザさんが演じている姿そのままのルックスの設定らしく、読者モデルから編集者になった人。見た目の派手さと、それを充分な武器として社会で生きてきた人。異常なほどきれいな人の人間性にスポットをあてている。
見た目が美人だったりイケメンだったりして目立つ人は、自然と周りから注目を浴びて人が集まってくる。岸辺みどりさんも、見た目の良さで、苦労せずとも人間関係ができてきてしまう人。ちょっとくらいわがままを言っても、周りの人たちは崇拝者なので聞いてくれてしまう。でも、ルッキズムでできた関係は、見た目からゆえ厳しい評価も受けやすい。普通の人なら許される失敗でも、幻滅されて致命的な過ちにもなりかねない。見た目が良いぶん、世間の目が厳しい。日頃の嫉妬心もあるので、周囲のひんしゅくにバイアスがかかる。きつしか四面楚歌に陥ってしまう。ある意味これも生きづらさ。
ドラマ版だけのオリジナルで、『星の王子さま』からの引用がある。岸辺さんは、自分はわがままな赤い薔薇だという。『星の王子さま』では、それこそ主人公の星の王子さまか、後半に登場する作者の分身のパイロットに感情移入するものとばかり思っていた。星の王子さまは、わがままな薔薇とケンカをして、薔薇の側から去ってしまう。薔薇は星に根が張っていて動けない。王子さまに逃げられてしまった薔薇。自分は本を読んだときは、薔薇は自業自得だと思っていた。
星の王子さまは旅をしてさまざまな人と出会っていく。王子さまが出会う王様や実業家、呑助とか、みんな物質主義者たちばかり。「昔は子どもだったことを忘れた人たち」と星の王子さまは一蹴する。夢を見ることを忘れてしまった人たちを批判する。でも自分も歳を重ねて感じるのは、星の王子さまが嫌った人たちが、必ずしも大人だとは思えないということ。ニーチェはパワーアップした子どもを超人と呼んだ。超人は大人のメタファー。詩人の谷川俊太郎さんは、「歳をとるのも悪いことばかりではない」と言う。「実年齢の老人の気持ちは当然わかるが、かつて自分が経験した年齢の感覚もすぐ思い出すことができる」と。本当の大人は、子どもの気持ちを持ったまま大人になった人。普段は大人として振る舞っているが、いつでも子どもの気持ちにすぐアクセスできる。そうなると、星の王子さまが批判した「子どもだった頃を忘れた人たち」も、生きづらさを抱えた人たちとなる。星の王子さまに捨てられて、ひとり残されたわがままな赤い薔薇の気持ちを想像すると、とてもやるせなくなってくる。
ドラマ版の岸辺さんは、いつも自分のことばかり話している。それを周りの人たちが、話を聴いてあげているといった構図がずっと続く。日本のドラマを自分が観慣れていないからなのか、ドラマ独特の自分語りのスタイルは、あまり得意になれない。でも、自分が悶絶するほど退屈だった場面でも、ネットでは神回と言っている人もいる。感覚というのは人それぞれだと感じた。いつしか自分は、自己中心的な岸辺さんにイライラし始めていた。ドラマの主人公なので、ギリギリのところで視聴者に嫌われないように性格設計されてはいるものの、実際にこんな人がいたら、やっぱり嫌われてしまうだろう。岸辺さんは境界性パーソナリティ障害(BPD)に近いのかもしれない。ドラマ版の『舟を編む』のテーマは、精神疾患を持った人が、打ち込めるものを見つけて、他者と協調できるようになっていく物語。草食系男子のままおじさんになった人に囲まれているので、ルッキズムは通じない。岸辺さんにしてみれば、熱中できるものはとくに辞書づくりでなくても良かったことになってしまう。ある意味、小説『舟を編む』の設定を借りた別の物語として、上手に成立させている。
本来の主人公の真締さんはASD。原作発表時は、発達障害なんて概念は一般的ではなかった。この10年で日本も大幅に研究が進んで、真締さんくらいにコミュニケーション能力があれば、特性があっても社会でやっていけるようになってきた。むしろ原作の冒頭で、真締さんに営業の外回りを担当させてしまっていた会社の人事の采配の甘さの方が大問題。適材適所に人を配置できなければ、企業自体も損害ばかりつくってしまう。辞書編集部に異動になった真締さんは、水を得た魚の如く仕事にのめり込んでいくのは至極当然。
真締さんがパートナーに選ぶ香具矢さんは板前さん。真締さんが研究者で、香具矢さんは職人。双方道を極める人たちなので、気が合うに決まっている。そしてこの2人は、世間的にはマイノリティにあたる。映画はこの2人の恋愛を主軸にしている。恋愛ものが苦手な自分は、この映画版ですら湿度を感じた。だからこそドラマ版のおセンチさが辛かった。でも日本のテレビドラマはこれくらい甘ったるいものなのだろう。自分の体質では糖尿病になりそう。
原作や映画版では、辞書づくりの15年の間にいくつかの命も終わりを告げていく。それこそ12年前の映画版に出演していた加藤剛さんや八千草薫さんも、すでにこの世を去っている。書物を始め、何かの表現を残すということで、それが誰かの目に留まる。その時点でその表現は、表現者を離れてひとつの個性を持ち始める。表現は生き物だ。自分の周りには、文章を書いたり、表現を発表している人が多い。その作品をみていたりしていると、しばらく会っていなくても会っているような錯覚に陥る。もう亡くなっている作家のエッセイなどを読んでいると、目の前で自分のために話をしてくれているような気さえしてきてしまう。
辞書づくりは複数のスタッフで編纂されている。携わる人の誰かが途中で命絶えたとしても、ほかの誰かがそのバトンをかならず繋いでいる。たとえその人が辞書の完成が見れないとしても、そこに関わっていた時間は永遠となる。その仕事が楽しくて仕方がない。たとえ結末が見れないとしても、それは不幸なことではない。幸せなひとときを迎えられたと、後悔など微塵もないだろう。天寿には限りがあるけれど、表現を残すことは永遠への道。
辞書づくりの姿をみて、言葉に対してこれだけ真摯に向き合うことなど、忙しい現代ではすっかり忘れていたと気づかされる。情報過多で物質主義、経済第一の世の中では殺伐としてくるのはあたりまえ。2024年に制作されたドラマ版は、紙媒体の衰退とネットの言葉の氾濫にも触れている。自分も紙媒体のデザイナーを生業としているので他人ごとではない。豊かさとはなんだと問われると、経済的な豊かさをすぐ思い浮かべてしまう。でも本当の豊かさは金銭では測れないもの。丁寧にひとつひとつのことに向き合っていく。それこそ真の豊かさなのだろう。だからこそ真締さんたちに読者は憧れてしまう。
日本語はよく出来ていて、それそのものを示す言葉が必ずと言っていいほど存在している。英語なら、ひとつの単語に複数の意味があり、話の前後から単語の意味を察していくようなつくりになっている。日本語のように的確な言葉が存在している以上、もしそれを間違えて使ってしまったら大変なことになってしまう。相手に対して配慮がなければ、その人が使う言葉にその人の心がそのまま反映してしまう。本人に意図はなくとも、その本心はダイレクトに相手に伝わってしまう。言葉は心の鏡。
自分の子どもがまだ3歳くらいだったころ。まだ言葉を覚えて始めたばかりの年代。自分がどこかへ行こうとしたとき、なんだか騒いで意思表示してくる。たくさん喋っている。言っている意味がわからないので、うるさいなと怒りそうになる。よく聴いてみると、自分がスマホを忘れて行ってしまいそうなので、必死に教えてくれようとしてくれていたのがわかった。危うく理不尽に叱りそうになった自分に猛省。むやみに怒ったりしたら、その子がどんな思いをするか。子どもにとって一生の傷になりかねない。子どもは本来正直な生き物。誠実な態度をとっているのに、大人がそれをわかってあげないからこそ性格が歪んでいくのだと感じた。それからは子どもが何かを話しているときは、少し丁寧に耳を傾けてあげることにした。「まだ言葉を知らないだけで、変なこと言ったことないよね。待ってるからゆっくり話して」と言ってあげると、子どもは「変なことなんて言うわけがない」と、したり顔で話を続けてくれた。
うつ病治療やそれの防止のための認知行動療法に、頭の中で考えていることを紙に書き出したり、言葉にしてみたりするのを意識的にやってみるというものがある。外在化というらしい。そうして具現化することによって、頭の中が整理されてたり、気持ちが晴れたりする。ブログを書くこともそれにあたる。井戸端会議は悪いもののように使われがちだが、雑談力がある人は、それだけでストレス解消ができてしまっている。言葉を形にすることで、治癒効果があるということ。
さまざま切り口のメディアミックス作品『舟を編む』を通して、言葉についてちょっと考えることができた。善良だけど変人だった真締さんが、仕事や恋愛を通して、人間らしく変わっていくことはとても面白い。まるでロールプレイングゲームで、だんだん強くなっていくみたい。「生きること」は「変わること」なんだと、岸辺さんは言っていた。いつしか自分もネットで活字を読むよりも、書物で活字を読んでいくことに意識し始めた。紙に書かれたり印刷された文章を読むことで、脳がリラックスしていくのを感じる。これは端末の画面では絶対に得られないもの。本を読むのはとても贅沢だ。
|
|
|
|
|
|
|
|
関連記事
-

-
『ルパン三世 ルパンvs複製人間』カワイイものは好きですか?
先日『ルパン三世』の原作者であるモンキー・パンチさんが亡くなられた。平成が終わりに近づいて、
-

-
夢は必ず叶う!!『THE WINDS OF GOD』
俳優の今井雅之さんが5月28日に亡くなりました。 ご自身の作演出主演のライ
-

-
『スーパーサラリーマン佐江内氏』世界よりも家庭を救え‼︎
日テレの連続ドラマ『スーパーサラリーマン佐江内氏』の番宣予告をはじめて観たとき、スーパーマン姿の堤真
-

-
『ベニスに死す』美は身を滅ぼす?
今話題の映画『ミッドサマー』に、老人となったビョルン・アンドレセンが出演しているらしい。ビョ
-

-
『パンダコパンダ』自由と孤独を越えて
子どもたちが突然観たいと言い出した宮崎駿監督の過去作品『パンダコパンダ』。ジブリアニメが好きなウチの
-

-
『初恋のきた道』 清純派という幻想
よく若い女性のタレントさんを紹介するときに「清純派の◯◯さん」と冠をつけることが多い。明らかに清純派
-

-
『デザイナー渋井直人の休日』カワイイおじさんという生き方
テレビドラマ『デザイナー渋井直人の休日』が面白い。自分と同業のグラフィックデザイナーの50代
-

-
『モモ』知恵の力はディストピアも越えていく
ドイツの児童作家ミヒャエル・エンデの代表作『モモ』。今の日本にとてもあてはまる童話だ。時間泥棒たちに
-

-
『オッペンハイマー』 自己憐憫が世界を壊す
クリストファー・ノーラン監督の『オッペンハイマー』を、日本公開が始まって1ヶ月以上経ってから
-

-
『攻殻機動隊 GHOST IN THE SHELL』 25年経っても続く近未来
何でも今年は『攻殻機動隊』の25周年記念だそうです。 この1995年発表の押井守監督作
- PREV
- 『さらば、我が愛 覇王別姫』 眩すぎる地獄
- NEXT
- 『ひとりでしにたい』 面倒なことに蓋をしない










