『スノーデン』オタクが偉人になるまで
スノーデン事件のずっと前、当時勤めていた会社の上司やら同僚がみな、パソコンに付属されているカメラを付箋やら絆創膏でかくしていた。真っ先に浮かんだのは『2001年宇宙の旅』にでてくるコンピューターHAL。カメラの向こうで誰が監視してるか分からない。自分もとくに疑問も感じず、それ以降はパソコンのカメラは隠すようにしていた。
映画『スノーデン』は、社会派のオリバー・ストーン監督の最新作。本人からは「最後の作品になるかもしれない」と言われている。2013年に実際にあった元CIA局員のエドワード・スノーデンによる、CIAの情報収集の手口を告発した事件を描いている。
個人情報のダダ漏れやそれらを操作できる、完全な監視社会。いままではSFだけの世界が、まさに現実のものとなっている。このスノーデン事件は、当時はセンセーショナルだったが、今では常識となってしまっている。ウェルカム・トゥ・ザ・ディストピア!
スノーデンは日本にも赴任していて、もし日本がアメリカの同盟から外れたら、一発で日本をブラックアウトさせられるらしい。とても興味深い。
オリバー・ストーン監督が、この映画のプロモーションで来日したとき、日本人インタビュアーを決して怒らせたり不快にさせたいわけではないと、丁寧な説明の上で「日本はまだアメリカの属国のままなんですよ」と言っていた。そうなると国内のさまざまな不条理も合点があう。
当時のアメリカ大統領のオバマは、スノーデンのリークを、「テロリストの仕業」と言った。のちに、いきすぎた情報収集を規制するよう指示した。ひとりの勇気ある行動が国を動かした。ただその規制はアメリカ国内に住む人のみ。しかも移民にはこれは適用されない。ならば日本の個人情報も、完全に脅かされていることになる。
日本も舞台の一つとなったこの映画。よく日本公開できたなぁと一瞬思ったが、2017年の現在はもっとすごいことになっているのかもしれない。この映画『スノーデン』の公開はガス抜きみたいなものなのかも。
組織に属していると、個人では絶対にしないようなことをしなければならないこともある。それは時に倫理に反したことだったりもする。上からの命令だからと、非人道的なことも割り切ってやってしまう。命令を下す上層部は、現場の空気感はわからない。組織の利益のために他人を陥れたり、騙したりもする。その究極は戦争。殺人も正当化されていく。
社会で働いていると、まったくクリーンではいられない。カネや慣例、縦割り社会など、しがらみで、犯罪まではいかないが道を外れることもある。限りなく黒に近いグレー。
人の役に立ちたいと選んだ仕事で、かえって人を悲しませていることの矛盾。お堅い仕事に就いている人に、犯罪者が増えているのも、その矛盾に押しつぶされてしまったからなのかもしれない。 理不尽な世の中で生きていくには、開きなおるタフなメンタルを築いていくしか方法がないのだろうか? 社会の歪み。
会社はそれをやれと言う。仕事だから仕方がない? そこは自分自身の心と相談しなければならない。
映画『スノーデン』はあくまで映画。観客にわかりやすくしなければいけないし、監督はオリバー・ストーンだし、視点はザックリとシンプル。
エドワード・スノーデン本人は、知的で疲れた印象の青年。映画は彼の半生を遡る。最初から今のスノーデンのイメージで描かれているが、実際は違かったのではないだろうか。
ただのオタクでサイコパスだったスノーデンが、いろいろ己の矛盾に悩むうちに、いつの間にか知的にならざるを得なかったのではないだろうか。
映画のスノーデンは終始、道を踏み外したりはしない。命令がどうであれ、正しいことは正しい、間違ったことは間違いだと、しっかりとした意志を持っている。しかし人はそんなに強くない。ひとりの青年が「これは国のためなんだ」と言い聞かせながら手を汚していく。傷つき病になり、自分の心と対峙する。心が告げる答えは、祖国の命令とは真逆だったということ。
何かをするとき、ザワザワっとイヤな感じがすることがある。きっと自分の心が拒否反応を起こしているのだろう。本能的な野生の直感。たとえ大義名分があったとしても、そんなときは自分の心と向き合った方がいい。自分で考えて答えを出す。その答えは十人十色。
エドワード・スノーデンは、世の中を動かした偉人だが、母国アメリカでは反逆者。視点が違えば立場が違う。現在モスクワに住む彼を、安息の日々を送っているように映画は伝えている。観客を安心させるオリバー・ストーン監督の心遣い。でも実際はもっと複雑な感情で、スノーデンは日々過ごしているだろう。
仕事だから、カネのためだからと、自分の心の声にフタをしてしまうのは、恐ろしいことだ。
決して偉人にならずとも、自分に正直に生きていきたいものだ。実はそれがいちばん難しいというのは、いかに世の中が生きづらいかという証明だろう。
関連記事
-

-
『私をくいとめて』 繊細さんの人間関係
綿矢りささんの小説『私をくいとめて』は以前に読んでいた。この作品が大九明子監督によって映画化
-

-
『MEGザ・モンスター』 映画ビジネスなら世界は協調できるか
現在パート2が公開されている『MEGザ・モンスター』。このシリーズ第1弾を観てみた。それとい
-

-
『ドグラ・マグラ』 あつまれ 支配欲者の森
夢野久作さんの小説『ドグラ・マグラ』の映画版を久しぶりに観た。松本俊夫監督による1988年の
-

-
『WOOD JOB!』そして人生は続いていく
矢口史靖監督といえば、『ウォーターボーイズ』のような部活ものの作品や、『ハッピー
-
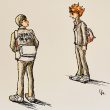
-
『ハイキュー‼︎』 勝ち負けよりも大事なこと
アニメ『ハイキュー‼︎』の存在を初めて意識したのは、くら寿司で食事していたとき。くら寿司と『
-

-
『ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限界かもしれない』ブラックって?
ネット上の電子掲示板『2ちゃんねる』に たてられたスレッドを書籍化した 『ブ
-

-
『窓ぎわのトットちゃん』 他を思うとき自由になれる
黒柳徹子さんの自伝小説『窓ぎわのトットちゃん』がアニメ化されると聞いたとき、自分には地雷臭し
-

-
『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』虐待がつくりだす歪んだ社会
ウチの子どもたちも大好きな『ハリー・ポッター』シリーズ。こわいこわいと言いながらも、「エクスペクト・
-

-
『レディ・プレイヤー1』やり残しの多い賢者
御歳71歳になるスティーブン・スピルバーグ監督の最新作『レディ・プレイヤー1』は、日本公開時
-

-
原作への愛を感じる『ドラえもん のび太の恐竜2006』
今年は『ドラえもん』映画化の 35周年だそうです。 3歳になる息子のお気
- PREV
- 『君の名は。』株式会社個人作家
- NEXT
- 『ボーダーライン』善と悪の境界線? 意図的な地味さの凄み





